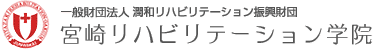学校案内
>
- 学校案内>
- 代表理事・学院長あいさつ
代表理事・学院長あいさつ
教育理念
隣人愛
自分を愛するが如く 他人を思いやり 気遣う心を養いなさい
地域に根ざした理学療法士の養成
学院設立の趣旨
全人間的復権の理念をもつリハビリテーションが、医学の世界に導入されたのは、おおよそ半世紀余り前のことです。その後のリハビリテーション医学は格段の進歩を遂げ、わが国においても「リハビリテーション」という言葉は広く国民の理解を得るまでに浸透してきました。
我が一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団は、早くからリハビリテーションの有用性に着目し、その研究・普及・啓発・実践に努めてきました。その一環として、リハビリテーション専門職の養成がリハビリテーションの推進に不可欠であるとの思いから、リハビリテーションという言葉さえ馴染みのない時代(1982年)に本学院を設立し、障がいをもたれた方々の社会復帰を念じつつ理学療法士の養成を手がけてきました。
時は流れ、現在ではリハビリテーション専門職が数多く輩出され、身近にリハビリテーション医療が享受できる環境になったことは大変喜ばしいことと感じています。しかしながら、今後とも高齢化の進展に伴い、理学療法士の活躍の場、およびリハビリテーションに対する期待はますます高まると思われます。
本学院は財団の医療ゾーンの一角に位置し、いつでも臨床現場が体験でき、将来の職業像を身近に感じることができる教育環境を活かし、また、可能な限り負担の少ない学費設定に心がけながら、質の高い理学療法士を育成し、地域住民の健康と福祉に寄与することを目指しております。

代表理事 大野順子

学院長 鶴田和仁